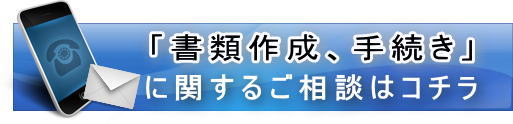「相続できない、相続させない」というケース
相続人本人がさきに亡くなっている場合は当然ですが相続できません。しかし、本来相続する権利がありながら、それを失ったしまう場合があります。それは相続欠格、相続廃除といいますが、どんな場合をいうのでしょうか。
相続欠格とは犯罪行為などで相続の権利が剥奪される場合をいいます
被相続人を虐待したり、重大な侮辱を与えたときに廃除することができ、被相続人は家庭裁判所に審判の申し立てをし、家裁がその申し立てを認めたときにはじめて、相続廃除が成立します。また、相続廃除は遺言によってすることも可能です。その場合は遺言執行者が家庭裁判所に申し立てることになります。
なお、相続欠格、相続廃除が行われるのは、それの対象となる者だけで、他の相続人に影響は及ぼしませんし、相続欠格者からの代襲相続を妨げるものでもありません。
つまり、子、孫、あるいは兄弟姉妹の場合の甥、姪など、法定相続人の権利は残ります。
しかし、そうした遺産相続をすべて被相続人の意思に任せてしまうと、極端な財産処分が行われることもあります。
個人の財産といっても、その財産は多かれ少なかれ、家族の支えを前提に形成されてきたものであり、残された家族の生活が今まで通り、維持、継続されることも、社会的な公平さの観点からも考慮されるべきでしょう。
このような点から、個人の財産とはいえ、遺産の自由な処分の範囲を一部制限しようという制度が、遺留分制度と言われているものです。
この遺留分は、被相続人が遺言で決めている場合のほか、あらかじめ生前に贈与で分けてしまった遺産も対象になります。
ただし、この遺留分は相続開始後の制度であって、被相続人の生前の財産処分の方法を妨げるものではありません。この意味は、相続人は生前に被相続人が自分の財産をどのように処分しても、それに関して異議を唱えることはできないということです。
つまり、相続人は被相続人が故人となったあとにはじめて、自分の遺留分を権利として、その取戻しを請求することができるのです。
子どもが亡くなっている場合は、代襲により、孫が遺留分を相続します。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
相続分が法律で定められているように、遺留分は法定相続分の二分の一と定められております。ただし、遺留分が認められている相続人のうち、配偶者も子もいないときの父母の相続に限り三分の一とされています。
B 相続開始前の1年以内に贈与された財産
C 1年以上前の贈与であっても、遺留分の権利者に損害を与えようとした意図で、贈与が行われている場合の贈与財産
ここから、「被相続人の負債 D」を差し引いた額が、算定の際の基礎額となります。
A+B+C-D=遺留分算定の基礎額
以上の基礎額に、遺留分の率を掛けたものが、相続人各自の遺留分となります。
この請求は、相続開始、あるいは侵害されていることを知ってから1年以内で、それを過ぎると請求権は消滅します。この請求に特別の手続きはありませんが、意思表示を明確にするには、侵害された各自が意思表示する必要があります。その際、内容証明郵便などを使用する場合もあります。なお、減殺請求の権利は、贈与や遺贈があったことを知らない場合でも、相続開始から10年が経過すれば権利は消滅します。
順序としてはまず、遺贈を受けた人に対し、それでも不足している場合は、新しい順に生前贈与を受けた人に対して行います。また、遺贈が複数ある場合は、遺贈の額に応じた按分比例になります。不動産など分割できない財産の減殺の場合は、その分を金銭で弁済することもできます。
たとえば、家業を子どもの一人に継がせるため、あるいは妻の老後を考えて、全財産を妻に与えるために、他の相続人が遺留分の放棄をあらかじめ行うという場合です。相続開始前に行う場合は、家庭裁判所に申し出なくてはなりません。それは放棄する当事者の相続人の意思を尊重するためです。
相続欠格とは犯罪行為などで相続の権利が剥奪される場合をいいます
- 相続で自分より先の順位の相続人を殺害、もしくは未遂があった場合
- 被相続人が殺害されたことを知っていながら、告発、告訴しなかった場合
- 詐欺や脅迫により、被相続人の遺言書の作成の変更などを強制した場合
- 被相続人の遺言の偽造、変造、破棄、隠匿を行った場合
被相続人を虐待したり、重大な侮辱を与えたときに廃除することができ、被相続人は家庭裁判所に審判の申し立てをし、家裁がその申し立てを認めたときにはじめて、相続廃除が成立します。また、相続廃除は遺言によってすることも可能です。その場合は遺言執行者が家庭裁判所に申し立てることになります。
なお、相続欠格、相続廃除が行われるのは、それの対象となる者だけで、他の相続人に影響は及ぼしませんし、相続欠格者からの代襲相続を妨げるものでもありません。
つまり、子、孫、あるいは兄弟姉妹の場合の甥、姪など、法定相続人の権利は残ります。
遺留分について
遺留分とは最低限、保証された相続割合のことといい、この設定は、極端な遺産分割を避けるのが狙いでもあります。個人が財産を自分が死んだ後にどのように遺すのかは、原則その人の自由です。しかし、そうした遺産相続をすべて被相続人の意思に任せてしまうと、極端な財産処分が行われることもあります。
個人の財産といっても、その財産は多かれ少なかれ、家族の支えを前提に形成されてきたものであり、残された家族の生活が今まで通り、維持、継続されることも、社会的な公平さの観点からも考慮されるべきでしょう。
このような点から、個人の財産とはいえ、遺産の自由な処分の範囲を一部制限しようという制度が、遺留分制度と言われているものです。
この遺留分は、被相続人が遺言で決めている場合のほか、あらかじめ生前に贈与で分けてしまった遺産も対象になります。
ただし、この遺留分は相続開始後の制度であって、被相続人の生前の財産処分の方法を妨げるものではありません。この意味は、相続人は生前に被相続人が自分の財産をどのように処分しても、それに関して異議を唱えることはできないということです。
つまり、相続人は被相続人が故人となったあとにはじめて、自分の遺留分を権利として、その取戻しを請求することができるのです。
遺留分の権利者と割合
相続人のうち、遺留分が認められているのは、配偶者と子ども、父母です。子どもが亡くなっている場合は、代襲により、孫が遺留分を相続します。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
相続分が法律で定められているように、遺留分は法定相続分の二分の一と定められております。ただし、遺留分が認められている相続人のうち、配偶者も子もいないときの父母の相続に限り三分の一とされています。
遺留分の算定方法と対象となる財産
A 相続開始時点の財産B 相続開始前の1年以内に贈与された財産
C 1年以上前の贈与であっても、遺留分の権利者に損害を与えようとした意図で、贈与が行われている場合の贈与財産
ここから、「被相続人の負債 D」を差し引いた額が、算定の際の基礎額となります。
A+B+C-D=遺留分算定の基礎額
以上の基礎額に、遺留分の率を掛けたものが、相続人各自の遺留分となります。
遺留分の減殺請求
実際の相続において、他の人への遺贈や生前贈与などが行われ、相続した額が法律で決められた遺留分よりも少なかったとき、侵害された権利の額について、遺贈や贈与を受けている人に、取戻しの請求ができ、これを遺留分の減殺請求といいます。この請求は、相続開始、あるいは侵害されていることを知ってから1年以内で、それを過ぎると請求権は消滅します。この請求に特別の手続きはありませんが、意思表示を明確にするには、侵害された各自が意思表示する必要があります。その際、内容証明郵便などを使用する場合もあります。なお、減殺請求の権利は、贈与や遺贈があったことを知らない場合でも、相続開始から10年が経過すれば権利は消滅します。
遺留分請求の方法
ある人の遺留分がいろいろなかたちで侵害を受けている場合、それに対する遺留分の減殺請求は誰に対して行えばいいのでしょうか。順序としてはまず、遺贈を受けた人に対し、それでも不足している場合は、新しい順に生前贈与を受けた人に対して行います。また、遺贈が複数ある場合は、遺贈の額に応じた按分比例になります。不動産など分割できない財産の減殺の場合は、その分を金銭で弁済することもできます。
遺留分の放棄
相続放棄は相続開始後しかできませんが、相続人の遺留分の放棄は相続開始前にも可能です。たとえば、家業を子どもの一人に継がせるため、あるいは妻の老後を考えて、全財産を妻に与えるために、他の相続人が遺留分の放棄をあらかじめ行うという場合です。相続開始前に行う場合は、家庭裁判所に申し出なくてはなりません。それは放棄する当事者の相続人の意思を尊重するためです。
下記のような場合には行政書士をご利用ください。
- 自分亡き後の財産の処分に思うところがある。
- 外出などできない状況にある。
- 相続が発生したが、何から手を付けていいか分からない。
- 自分でやるのは正直面倒なので、この際専門家に任せたい。
- 自分でやるつもりでいるが、思うように進まない。
- 相続人の足並みが揃わないので、公平な第三者に仕切ってもらいたい。
業務のお申し込みはこちらから
相続手続きの書類作成などの行政書士業務を承っております。
御見積りも無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
ご相談の申し込みはこちらから
行政書士への書類作成に関するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
業務対応地域
- 書類作成・手続きなどの行政書士業務は、札幌市内、近郊のお客様に対応しております。訪問してのご相談も無料です。